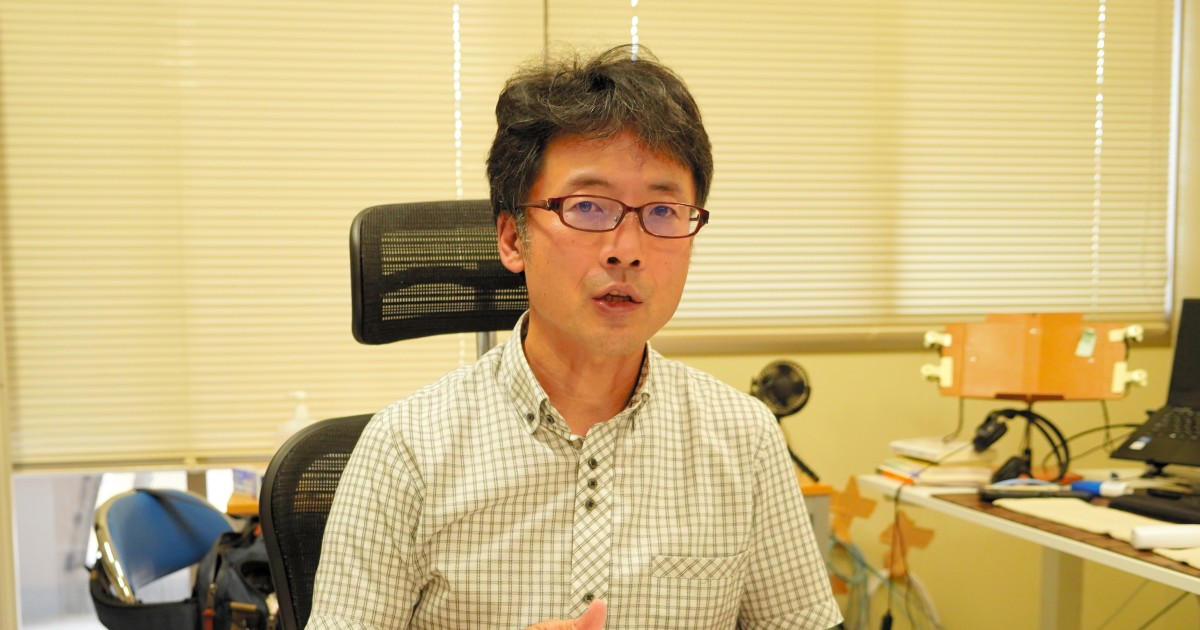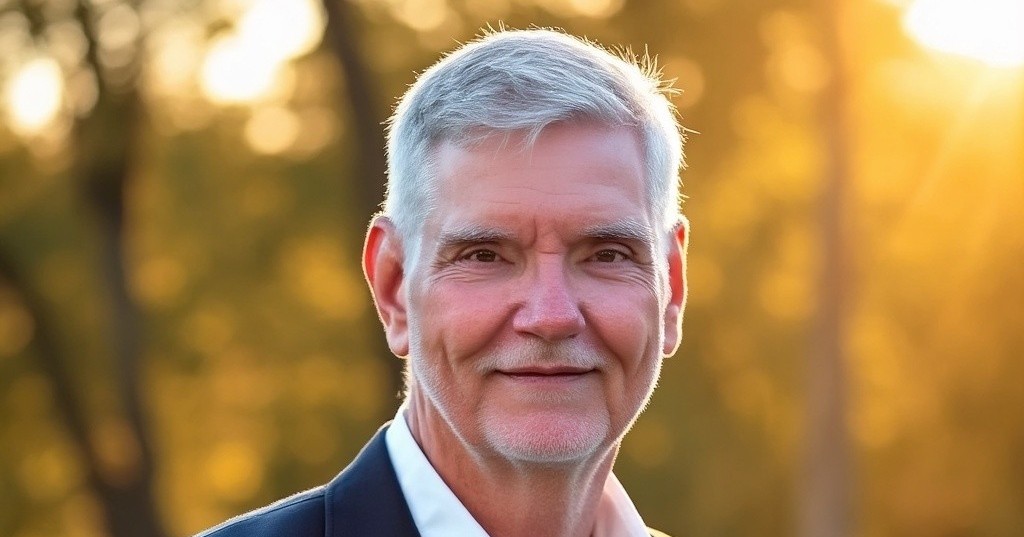台湾をめぐる日米の戦略と、揺らぐあいまいさ 高市政権が進むべき道とは?
最近、台湾を巡る日米トップの発言が注目を集めています。トランプ米大統領は2日、米CBSとのインタビューで台湾有事について「私が大統領でいる間は何もしないと(中国側が)率直に伝えてきた」と語りました。高市早苗首相は7日の衆院予算委員会で、台湾有事を巡って日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」にあたる具体例を問われ、「戦艦を使って、武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうるケースだと私は考える」と語りました。この二つの発言をどう読み解けばいいのでしょうか。

まず、二人の発言は、日米が従来取ってきた「あいまい戦略」とは異なります。中国が台湾を武力統一しようと試みた場合、台湾を防衛するかどうかを明確にしない戦略のことです。戦略には、武力衝突の可能性を下げる狙いがあります。「台湾を防衛しない」と明言すれば、中国が武力統一に踏み切る可能性が増えます。「防衛する」と言えば、中国を刺激するほか、台湾内部で独立論が強まりかねません。
もちろん、「あいまい戦略」にある程度の振れ幅はあってよいと思います。バイデン前大統領は在任中、5回にわたって台湾防衛の意思を示しました。当時、米国内で「2027年に中国が台湾に武力侵攻する可能性がある」という「2027年危機説」が強まっていました。バイデン氏の発言は、中国を強くけん制する必要があるという判断が働いた結果なのかもしれません。もちろん、ホワイトハウスはバイデン氏が「台湾防衛」を口にするたびに、「米国の公式見解ではない」と打ち消していました。
トランプ・高市発言、どう読み解くか
では、トランプ氏の発言をどう読み解けば良いのでしょうか。