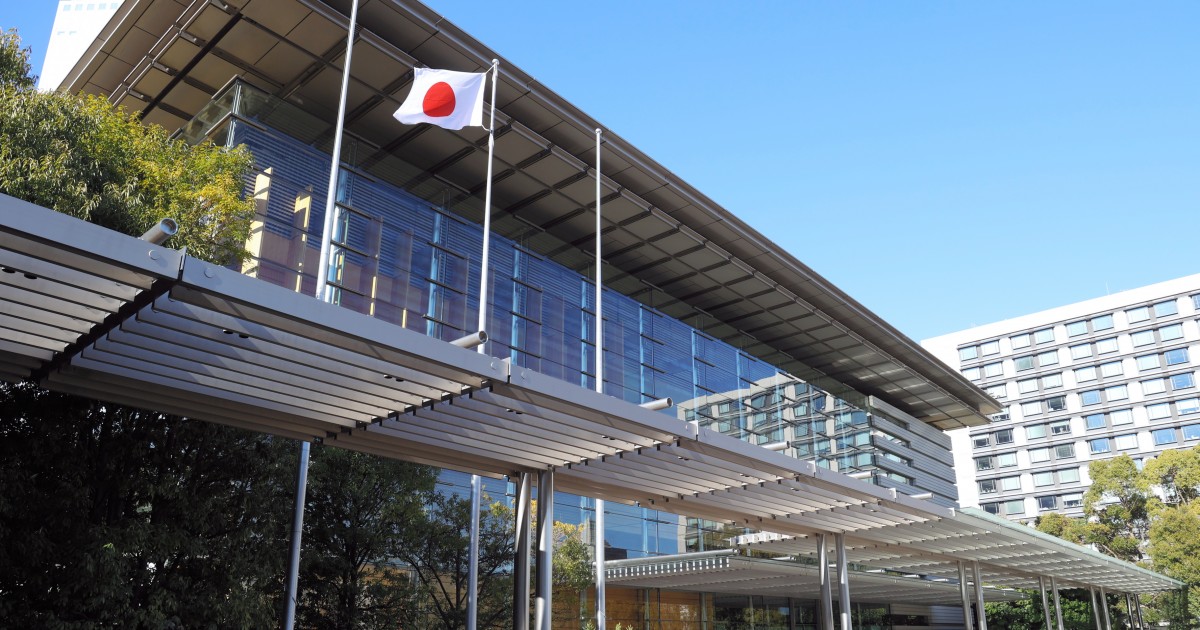紙一重だった戦後日本の行方と運命の分かれ道 80回目の終戦の日に考えた平和の大切さ
今年も8月15日がやってきました。第二次大戦の終戦から80年が過ぎました。日本は戦後、様々な人々の努力もあり、民主国家として平和な時代を過ごすことができました。同時に、戦中・戦後の様々な文書や、関連するやり取りについて取材してみると、日本が非常に幸運だった状況も浮かび上がります。
先の大戦では、軍人・軍属230万人、沖縄を含む在外住民30万人、内地の住民50万人の計310万人もの尊い命が失われました。もし、米軍が考えていた日本侵攻計画「ダウンフォール作戦」が実施されていたら、こんな数値では済まなかったでしょう。例えば、地上戦が繰り返された欧州のウクライナでは800万人以上が亡くなったと言われています。
日本が無条件降伏した理由とは
「ダウンフォール作戦」は1945年11月1日をもって南九州に侵攻するオリンピック作戦と、46年3月1日に関東に侵攻するコロネット作戦で構成されていました。米軍統合参謀本部連合戦略調査委員会が44年9月に作成した報告書では、「ダウンフォール作戦」で50万人の戦死者とその数倍の負傷者が出る可能性が指摘されていました。これに対し、日本側は「1億総特攻」を唱え、水際でただ1度きりの総力を挙げた特攻作戦を考えていましたから、米軍をはるかに上回る犠牲者が出たでしょう。
最終的に、日本がポツダム宣言を受け入れて無条件降伏したことで、報告書が指摘するような更なる被害を防ぐことができました。戦史の研究者たちの間では8月15日に日本が降伏した理由について、米軍による原爆投下やソ連の対日参戦、天皇の軍部への信頼喪失など、様々な分析が行われています。私は、これに加えて軍人や沖縄の人々の犠牲があったからこそだと考えています。トルーマン米大統領は45年6月17日付の日記で、なお「日本に侵攻するのか、それとも爆撃と封鎖をするのか」と悩みをつづっています。日本の激しい抵抗で米軍の死傷者が増大していたことを憂慮していたからです。

米ニューオーリンズの米国立第2次世界大戦博物館にある、米軍の「オリンピック作戦」(南九州侵攻)を説明する掲示物=2014年11月28日、牧野愛博撮影
米軍も単純に無条件降伏を突きつけただけではありませんでした。水面下では、「国体護持(天皇制の維持)」に必死になる日本政府に対し、知日派のジョセフ・グルー元駐日大使ら知日派が「天皇制の維持」を強く主張しました。グルーたちは日本に民主主義の経験があることを知っていたからですが、同時に米軍の犠牲者をこれ以上出させないよう早期終戦に持ち込むためには、天皇制の維持が必要だとも考えたようです。日本は米国の知日派に救われた面もあったと言えると思います。
4カ国共同占領プランも
一方、米国は45年までに天皇制を残す方針を決めていましたが、日本に対して軍政とするか間接統治とするかでは、意見が割れていました。