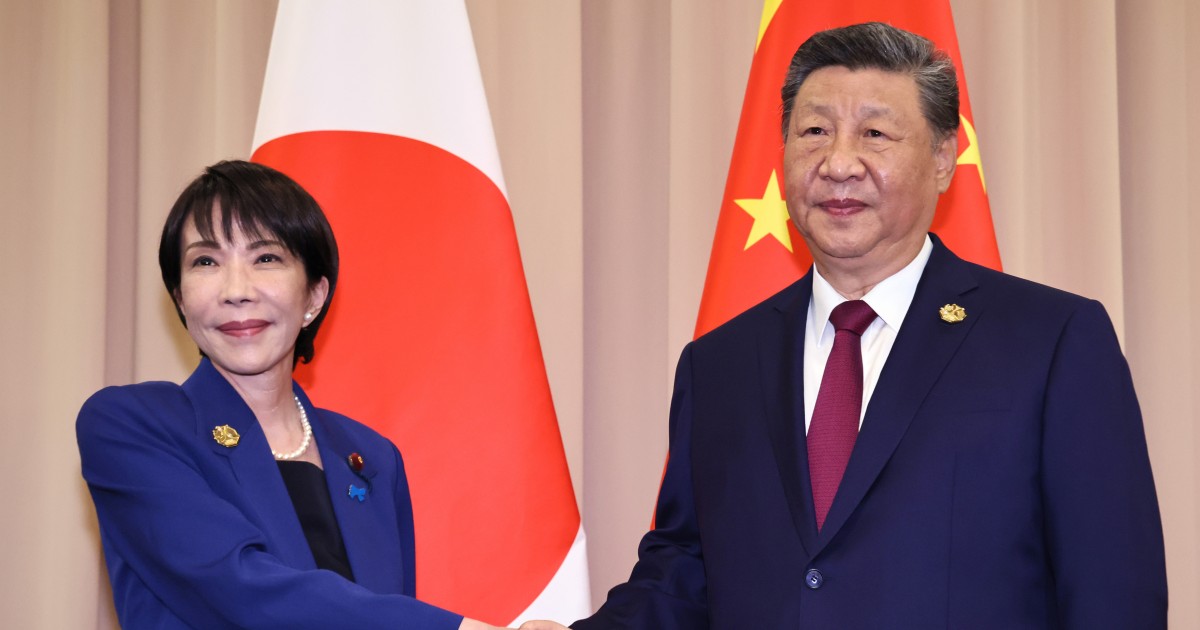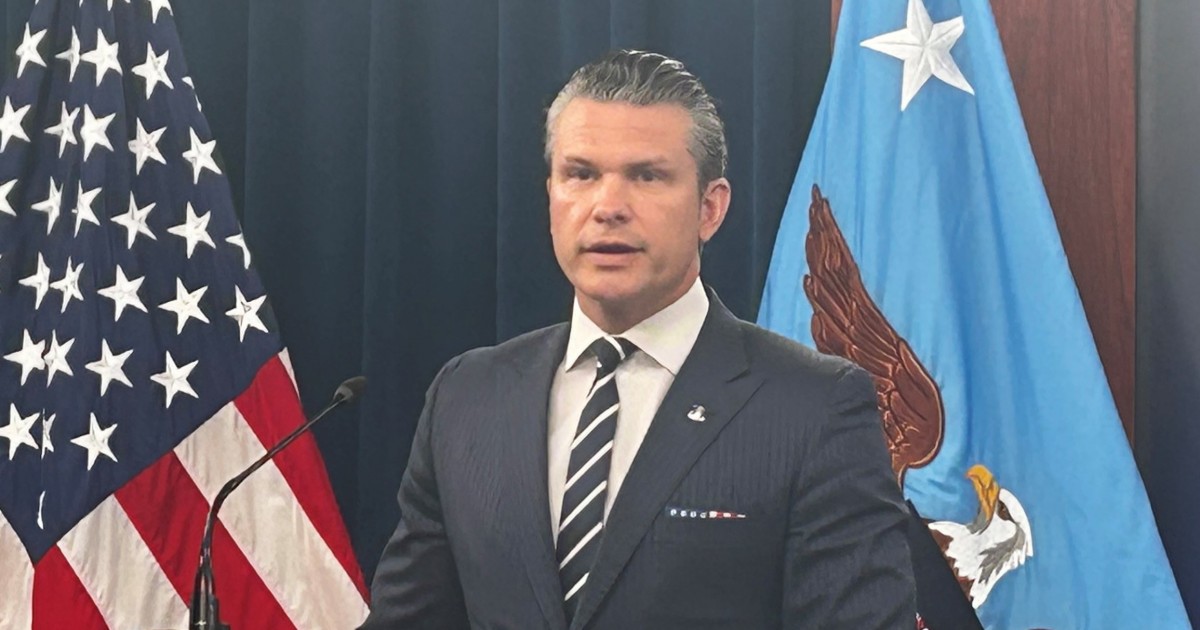ウクライナの現在と重なるフィンランド トランプ政権と向き合う日本、豊かな国を作れるか
「フィンランド化」
年配の方や欧州政治を勉強した方なら、この言葉に聞き覚えがあるかもしれません。冷戦時代の1983年夏、当時の中曽根康弘首相が参院選公示日の第一声で、「何もしないでいると、フィンランドのようにソ連にお情けを請うような国になってしまう」と演説しました。在日フィンランド大使館が「事実を反映していない」と外務省に申し入れ、中曽根首相がフィンランドのソルサ首相に、事実上、発言を撤回する親書を送ったそうです。
フィンランドは当時、旧ソ連との間で友好協力相互援助条約を結んでいました。フィンランドは、ソ連主導の軍事同盟だったワルシャワ条約機構への加入を免除される代わりに、ソ連に敵対する可能性を自ら否定する中立政策をとりました。それが、当時の中曽根首相には「お情けを請う」態度に見えたのでしょう。
そのフィンランドが今年4月、対人地雷全面禁止条約から脱退する方針を表明しました。対人地雷は兵士だけでなく、無差別に民間人にも被害を与える兵器として知られています。2024年の報告書によれば、23年に地雷による死傷者の83%が民間人で、37%が子供だったそうです。フィンランドの条約から脱退するという方針は、人権団体を中心に激しい批判にさらされました。

フィンランド・パロラにある戦車博物館。冬戦争や継続戦争などで使われた装備が展示されている=同博物館のホームページから
なぜ条約から脱退する方針なのか
ただ、最近、フィンランドに出張した専門家の知人に話を聞くと、「フィンランドもそのような批判が出ることは十分理解していた」と教えてくれました。フィンランド国内でも「国際的な約束を守るべきではないか」「国際的な信用が落ちてしまうのではないか」といった声があり、散々悩んだ末での決定だったそうです。何よりもフィンランドの世論も条約離脱方針を支持しています。
その理由は、80年前のフィンランドの姿が、現在のウクライナと重なる存在と言えるからです。
フィンランドとウクライナが重なるというのはどういうことでしょうか? 批判が渦巻く中でも対人地雷を復活させるという方針に潜む狙いを牧野記者が読み解きます。